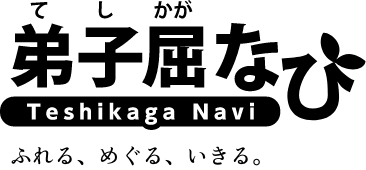2018.01.01
歴史写真館NO.26 啄木-わがこの心 何の心ぞ
 |
石川啄木が、故郷岩手県の渋民村の代用教員を「石もて追はるるごとく」後にして津軽海峡を渡ったのは、21歳の明治40年5月。2歳年下の妹・光子を伴って函館・小樽に、続いて妻子と母も後を追うようにやってきます。家族を小樽に残し、単身釧路駅に降りたのは明治41年1月21日。啄木の運命を変えた釧路新聞の記者としての生活はわずか76日間でしたが、代用教員時代の月給8円、函館での15円に比べ、30円の月給は大金でした。手にした30円と、単身であるという束縛のない境遇が啄木を変えます。酒を覚え、女を知り、ほどなく料亭での酒色を貪るようになります。啄木は、日記の中に多くの女性の名前を記してい ます。特に小奴こと近江ジンさんを「善い女」と記し、看護婦の梅川(小山)操さんを「悪い女」「危険な女」と身勝手に記しています。家族に送金したのは、19円と15円の2回34円のみ。下宿代すら払えず、その上借金を重ね「歩すること三歩、自分の心は決した。啄木釧路を去るべし、まさに去るべし」と日記に『決別の辞』を残し、4月5日朝、函館行きの酒田川丸に乗ります。
半独身の東京での生活(後に妻子と母と同居)は、朝日新聞の校正係として雇われ、歌人としての才能を見込まれ「朝日歌壇」の選者に抜擢されますが、下積みの生活は変わらず貧困にあえぎます。にもかかわらず、妻を裏切り、浅草で女郎遊びを繰り返します。金に困り借金を重ね、友人たちの「偽善」を容赦なく暴き、手負いの猪のごとくのたうち回りながらも、その両眼には奇妙なさめた光が差しています。魂の奥底にあった歌への一途さが、啄木の啄木たるゆえんでした。そして歌集『一握の砂』が世に出ます。
『一握の砂』に、盛岡中学をストライキで退学した15歳の時詠んだ歌があります。「不来方の/お城の草に/寝ころびて/空に吸はれし/十五の心」と、早熟の少年は心情を吐露しています。その後も自らの「こころ」の千変万化する姿態を歌の中に紛れ込ませようと、悪戦苦闘は続きます。「わがこころ/けふもひそかに/泣かむとす/友みな己(おの)が/道をあゆめり」「はても見えぬ/真直ぐの街を/あゆむごとき/こころを今日は/持ちえたるかな」。「こころ」が生煮えのまま、形も定まらぬままに、無造作に投げ出されています。「いらだてる/心よ汝(なれ)は/かなしかり/いざいざすこし/あくびなどせむ」「あたらしき/心をもとめて/名も知らぬ/街など今日も/さまよひて来ぬ」。「いらだてる心」「あたらしき心」と言いながら、その心のしんをつかみかねています。「人といふ/人のこころに/一人づつ/囚人がゐて/うめくかなしさ」「死ね死ねと/己を怒り/もだしたる/心の底の/暗きむなしさ」。悲しさ、むなしさと自問せざるを得ない心の彷徨を詠みつつも、その実体を問えば、手のひらの指の間からこぼれ落ちていく「囚人」の心です。「水晶の/玉をよろこび/もてあそぶ/わがこの心/何の心ぞ」
明治45年、肺結核を患った啄木の元に、夏目漱石夫人から見舞いの10円が届けられます。その日の日記に「いつも金のない日を送っている者がタマに金を得て、なるべくそれを使うまいとする心!それから またそれを裏切る心!私は悲しかった」と記します。しゃれこうべのごとく目、鼻、口がただの穴のように見えるほどに変貌した啄木は、4月13日午前9時30分臨終、26歳。6歳の長女が桜の落花と戯れていま した。
それから55年後の昭和42年9月15日、老人ホーム倖和園で一人の老婦人が息を引き取ります。啄木と今生で走馬灯のような縁を持った梅川(小山)操さんです。享年82歳でした。
てしかが郷土研究会(加藤)